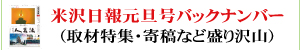|
書評 みちのく歴史探訪ー北の大地に思いを馳せて 斎藤秀夫著
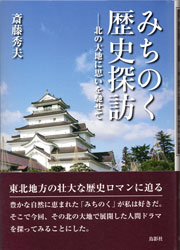 東京都八王子市在住で、城郭巡りや戦国武将の評伝などを著している作家、斎藤秀夫氏から新刊本が届いた。「歴史研究」などの専門家向けのみならず、平易な文体と登場人物にセリフを言わせて、小説風にする能力にも長けている。
東京都八王子市在住で、城郭巡りや戦国武将の評伝などを著している作家、斎藤秀夫氏から新刊本が届いた。「歴史研究」などの専門家向けのみならず、平易な文体と登場人物にセリフを言わせて、小説風にする能力にも長けている。
東北に住む者として、「みちのく歴史探訪ー北の大地に思いを馳せて」というタイトルがとても気に入った。本書はこれまで米沢御堀端史蹟保存会の会誌「懐風」や米沢日報紙、米沢日報デジタルに掲載された作品をまとめたものだ。斎藤氏は、講演で米沢を何度も訪ねており、東北に関しては土地勘もあってか、相当な思い入れを感じる。
「はじめに」の中で、「みちのくに住む人々は東日本大震災にくじけることなく、この自然の猛威にも屈しない、心の強さはどこからくるものであろうか?」「彼らを育んできた地域やその地で過去に展開してきた人間ドラマを探ってみたくなった」と述べている。
東北は中央から3度攻められ、負けた歴史がある。被害者意識で語れば、雪国の民を虐げ、いじめられてきたという歴史である。その一つ目は、奈良時代、坂上田村麻呂が征夷大将軍となり、エミシとの戦いで東北を征服したことであり、二つ目は源頼朝による奥州藤原氏の滅亡、三つ目は戊辰戦争での奥羽越列藩同盟の敗戦であろうか。本書は基本的にこの三つの戦いの歴史が根底にある記述であると思う。
本書には14編が掲載されている。みちのく歴史探訪というタイトルであるが、実は米沢が舞台だったり、米沢と関わりのある人物を紹介するものが中心にすえられていて、みちのくを米沢と置き換えても何らおかしくない。
米沢は、東北南部のへその位置にある。第一編の「米沢へ通じる道」では、米沢城下の札の辻を起点に、会津街道を始め、最上街道、板谷街道など5本の幹線道路を紹介する。道は人や荷物の往来を始め、政治、経済、文化往来の道である。その街道にまつわる歴史やエピソードを丹念に調べ上げた。読者はあたかもその場所を訪れたような気分になってくるだろう。何よりも斎藤氏の文章は、年輪を重ねてより味わい深いものとなった。
第三編の「阿津賀志山の戦い」では、斎藤氏はこの戦いを「エミシの血を引く奥州藤原一族と、清和天皇の血を引く源氏一族との、700年間にもわたる抗争の歴史に終止符を打った戦い」だったと述べる。歴史にもしもは禁物であるが、藤原泰衡が父親の言う通り、義経を殺さずに、大将に据えて頼朝と戦ったならば、一体どんな戦いとなり、どんな結末になっただろうかと思わず考えてしまう。この戦いで敗れて、100年続いた奥州藤原氏は滅びてしまう。そして、この論功行賞により、頼朝の側近として仕えた大江広元の子の長井時広が米沢を支配し、その後、伊達氏が領し、のちに米沢に伊達政宗が生まれることになる。
第七編の「上杉景勝という男」では、景勝の生涯を述べる。関ヶ原の戦いは、そのきっかけでは、徳川家康と上杉景勝という二人の役者がいた。その役どころの重要性と景勝が生涯無口だったというが、それが「上杉景勝という男」というタイトルに現れている気がしてくる。斎藤氏の景勝への見立ては、120万石から30万石へ削られたにも関わらず、家臣をほとんど召し放し(解雇)をしなかったことの「偉大さ」と述べ、景勝の懐の深さに感じ入っている。家臣を召し放ちしなかったことは、関ヶ原の戦いの次に備えてというのが一般的な理解だが、景勝の人情味に言及したのは面白い。
十二編の「至誠の人 上杉鷹山」では、若い藩主鷹山の改革路線に、藩の体面を訴えて異を唱える重臣の七人が起こした七家騒動を述べる。確かに、鷹山にとってこの七家騒動は、人生最大の危機だったろう。皆に尋ねて、事実を確認し、敢然とした処分を下した。須田満主・芋川正令に切腹、2名は隠居閉門、半知召し上げ、他3名は隠居閉門、知行300石の取り上げとなった。斎藤氏は、細井平洲に学んだことで、優しさの中にも厳しさを秘めた鷹山の人間性が読み取れるとする。ただ、天明の飢饉の際に米沢藩では一人の餓死者も出さなかったとするのは、鷹山を神格化をしようとする意図が感じられると述べる。評者も上杉鷹山の改革は、この七家騒動での決意があってであると思う。
第十三編の「奥の細道での芭蕉と曽良と出羽国」は、米沢日報デジタルに寄稿したもの。斎藤氏と評者は、芭蕉と曽良が酒田の浜中から大山に至る道をどのように歩いたか議論したことがあった。曽良の旅日記では、その部分が書かれていないからだ。浜中から大山に至る道の途中に、評者の故郷である鶴岡市善宝寺がある。浜中から海岸端を通って七窪から善宝寺に来るルートと、浜中から内陸部の長崎、面野山を通って善宝寺に来るルートがある。実は評者は、この斎藤氏の寄稿を初めて見てとても驚いたのである。これまで芭蕉と曽良が、善宝寺を通ったことを何十年と知らなかったからである。まさに灯台下暗しだった。
斎藤氏のみちのくに対する愛情がいっぱい溢れている本書を是非手にとって頂きたいと思う次第である。(評者 成澤礼夫)
出版社 鳥影社
発行日 2025年10月23日発行
価 格 1,500円+税